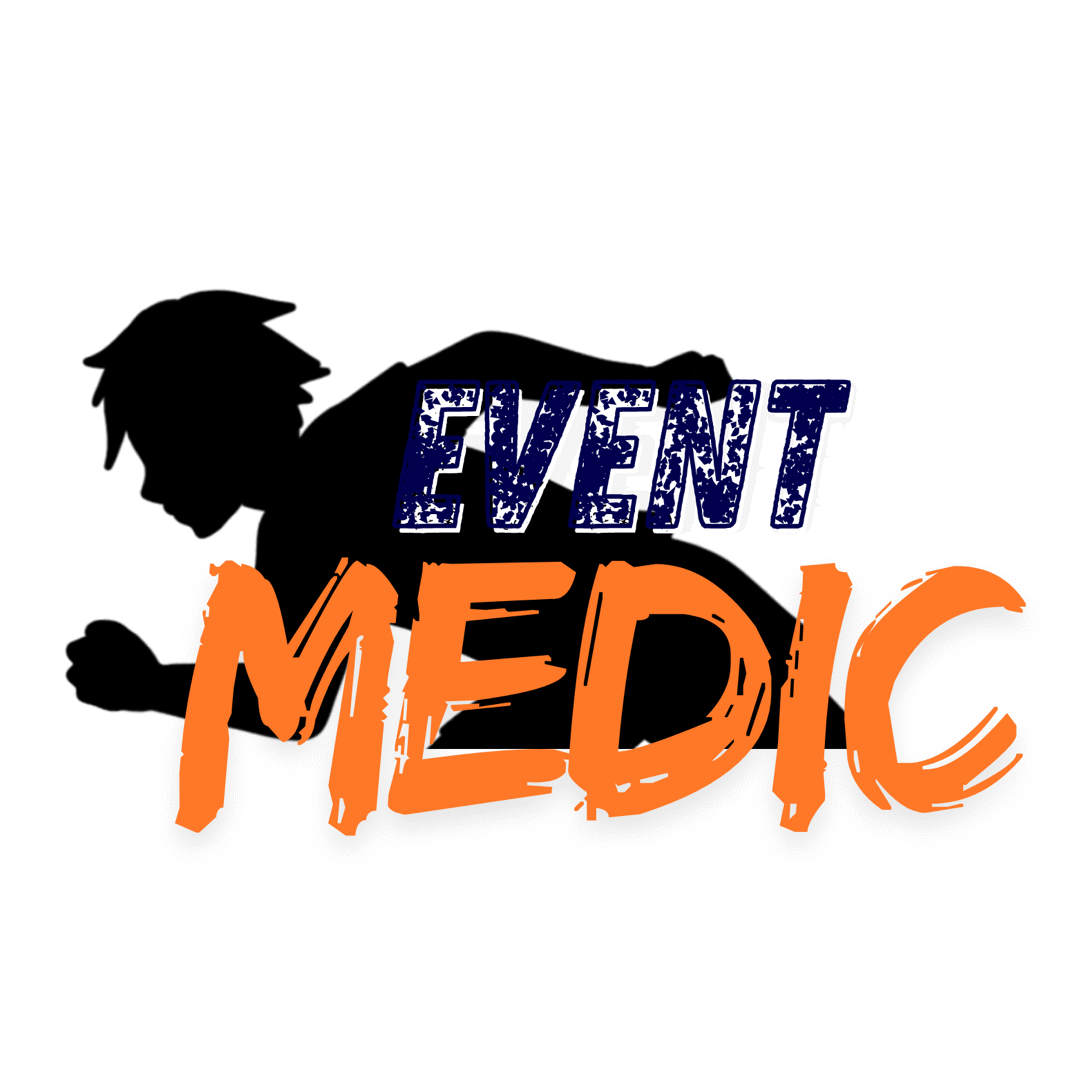新人教育における「普通」とは? 〜新卒スタッフへの教育で大切にしたいこと〜
新緑の季節、日々の気温差に迷いながらも、少しずつ春の心地よさを感じる時期になりました。寒暖差に悩みながらも新しい季節を楽しむこの時期に、ふと「普通とは何だろう?」と考えることがあります。
突然ですが、皆さんにとって「普通」とは何ですか?
この質問に対して、もしかしたら「そんなの当たり前だよ」とか、「それは普通のことでしょ」と思うかもしれませんが、ちょっと立ち止まって考えてみてください。なぜ、私たちは「普通」や「当たり前」という言葉を使うのでしょうか?それは、自分の基準や経験に基づいて、その言葉を使っているからです。
「普通」とは誰かの基準でしかない
私たちが日々使う言葉や行動には、自分の生活や経験が深く影響しています。例えば、ある職場では「これが普通」とされている仕事の進め方が、別の職場では「普通ではない」と感じられることもあります。私たちが当たり前と思っていることが、他の人にとってはそうではないことが多いのです。
これは、特に新人スタッフの教育において非常に重要なポイントです。新卒のスタッフが入社して、最初に直面する壁は「普通」や「当たり前」が自分と他人で異なることです。このギャップに気づくことが、成長への第一歩となります。
例1:数学の基本
例えば、算数で「-(マイナス)×-(マイナス)」が「+(プラス)」になると習うまで、私たちはその法則を知らなかったわけです。これは、私たちが当たり前に知っていることが、他の人には未知のことでもあるという良い例です。新卒スタッフにとって、「普通」という概念は、彼らがこれまで経験した世界の「基準」から始まります。
例2:職場での「普通」
各業界や企業の標準化された方法や文化、チームのやり方も、外の世界では「普通じゃない」かもしれません。例えば、ある企業では、細かいマニュアルや手順書に従って仕事を進めるのが「普通」ですが、別の企業では、柔軟に動くことを求められる場面が多いかもしれません。これも「普通」の違いです。
新人教育における「普通」の理解とそのギャップ
新卒スタッフが入社して最初に戸惑うのは、「普通の基準」が自分と周りの人で違うことです。だからこそ、私たちが新人に伝えるべきなのは、その違いを理解し、柔軟に対応できる力を育むことです。
1. 「普通」を共有する
新人教育の中で最初に大切なのは、「会社の普通」をしっかりと伝えることです。会社における「当たり前」をしっかりと理解してもらい、彼らが慣れ親しんだ外の世界とどのように違うのかを明確にすることが重要です。それには、単に業務フローやマニュアルを教えるだけでなく、なぜその方法が「普通」とされているのか、その背景や理由を説明することが大切です。
例えば、ある業務で「報告・連絡・相談」の3つのステップを踏むことが普通だとしても、それがどうして必要なのかを理解してもらわなければ、単なる「ルール」に過ぎません。その背景にある「チームで協力する意味」や「トラブルを未然に防ぐためのコミュニケーションの重要性」を伝えることで、より深く理解してもらえます。
2. 言葉の選び方
「普通に考えれば分かるでしょ?」という言葉をつい使ってしまうことがありますが、この言葉が新人にとっては大きな壁になることがあります。特に、新卒や経験の浅いスタッフにとっては、「普通」の基準がまだしっかりと定まっていないことが多いからです。彼らにとっては、新しい情報や環境が多すぎて、何が「普通」なのかをすぐに理解することは難しいのです。
そのため、具体的な説明や例を交えて伝えることが重要です。例えば、「普通に考えれば分かるよね」と言ってしまいがちな場面でも、なぜそれが「普通」なのか、具体的な背景や理由をしっかりと伝えることで、より深い理解が得られます。
3. 新人の「普通」を受け入れる
新人が抱える課題や疑問は、私たちが考える「普通」に当てはまらないことがあります。しかし、それは決して「間違い」ではありません。彼らが持っている「普通」を受け入れ、その違いを尊重することが、新人教育において最も大切な部分です。
例えば、学生時代に使っていた言葉遣いや仕事の進め方、考え方には、まだ社会人としての「普通」が十分に染みついていないことが多いです。それを注意する前に、まずはその考え方や行動の背後にある理由を理解し、適切にフィードバックをすることが、新人教育の第一歩です。
4. 「普通」を育むプロセス
新卒スタッフにとって最も大切なのは、単に「普通」を教えることではなく、その「普通」がどのように生まれ、どのように活かされているかを理解させることです。業務の進行やチームワークの中で自然にその「普通」が身についていくプロセスを大切にし、彼らが自ら「普通」を理解し、実践できるようにサポートしていきましょう。
「普通」を教えることは、新しい未来を作ること
新人教育は、単に業務を教えるだけではありません。「普通」を共有し、理解し、体現することによって、彼らは新しい価値観や視点を身につけて成長します。このプロセスこそが、組織の中で新しい風を吹き込み、未来を作り上げるための礎となるのです。
新卒スタッフへの教育は、その後の成長やキャリア形成に大きな影響を与えます。「普通」にとらわれず、柔軟に視野を広げ、相手の立場に立った教育を行うことが、スタッフ一人ひとりの成長を促し、組織の発展にも繋がります。
これからの時代、「普通」を超えて、もっと自由で多様な考え方が求められる時代です。新卒スタッフにとって、この「普通」の基準を理解し、適切に活用できる力を育むことが、私たちの大きな使命であり役割なのだと思います。
新年度が始まり、新卒スタッフとの関わりも深まってきた今、彼らと共に成長し、新しい「普通」を作り上げるための教育を行っていきましょう。それが、私たちの未来をより豊かにし、強くするための第一歩となります。